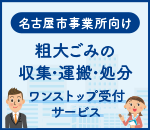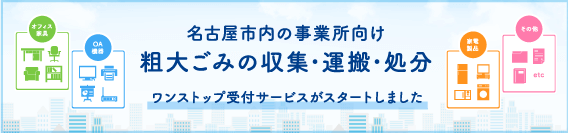最近よく聞くデジタルトランスフォーメーション(DX)ですが、改めてDXとは何かを説明できる人は少ないのではないでしょうか。
今回は、そもそもDXの定義とは何か、なぜこんなにも注目されているのかを解説していきます。
デジタルトランスフォーメーション(DX)とは何か
突然ですが、皆さんはスマートフォンをお持ちでしょうか。
総務省のデータによると、2021年の日本での保有率は88.6%だそうです。
スマートフォンは2007年のiPhoneの登場以来、爆発的に普及していきました。
iPhoneは登場当時、『全面タッチパネルになっただけの携帯』『手のひらサイズのコンピューター』など従来の製品から形を変えただけに思われていましたが、実際には手のひらサイズでいつでもどこでもネットに繋がることができる革新的な製品でした。
世界最大のオンラインサイトであるAmazonも、最初はネット通販書店でしたが日用品や自動車、動画や音楽などのデジタルコンテンツまで買えるオンラインストアとなり人々の暮らしを快適にしています。これらに共通するのはITを用いたビジネスだという事です。
デジタルトランスフォーメーション(DX)とはこのように“ITをつかって変化を起こし、売り上げや利益を伸ばす仕組みを作る事”と定義されています。
DXが注目されている3つの理由
①経済産業省のDXレポートがきっかけ
2018年に公開された経済産業省の『DXレポート~ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開~』の中で、「DXが進まないと2025年以降、最大で年間12兆円の経済損失が起こる恐れがある」という予想が立てられています。
②の項目で詳しく説明をしますが、ITシステムの老朽化による様々な問題が生じており、
経済産業省としては企業に危機感を抱かせてDXの推進をしたいということです。
https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/digital_transformation/20180907_report.html(経済産業省HP)
②産業支援として
日本では約8割の企業が古いITシステムを抱えていると言われています。
これらのシステムは、長年の継ぎ足しで複雑化をしている上に開発当時の社員がいなくなっているなど、ブラックボックス化してしまっているのが現状です。
これでは保守費や運用費がかさんでしまい、システム刷新を行う余力を奪い経営を圧迫する負債になってしまいます。このことをレガシーシステムといいます。
レガシーシステムにより、デジタル人材の不足や新しいサービスへリソースを割けないなど様々な問題がありますが、問題を抱えながらもまだ使えているレガシーシステムを切り替えたり新事業に投資をすることは経営層や株主の理解が得づらいものでもあります。
そこで、経済産業省は東京証券取引所と共同で「攻めのIT銘柄」「DX銘柄」として、IT活用に取り組む企業を選定、公表しています。
これにより、株式市場でも評価されるということを示し、企業のIT投資への評価を引き上げる狙いがあります。
③働き方改革に次ぐ施策として
働き方改革とは『一億総活躍社会』に向けて2016年から始動した取り組みで、簡単に言うと少子高齢化で減少する労働力を補うための取り組みです。
労働環境を改善することで働ける人を増やし、職場環境の改善による生産性の向上を図っています。
働き方改革を制度や意識の改善とすると、DXはそれを実現するための施策です。
働き方改革によって削減した時間に、ITを使って変化を起こし、売り上げや利益を伸ばす仕組みを作るのです。
DXの始め方
DXを始めるときの最初の壁は、ずばり「周囲の無理解」です。
周りの人は「新しい事は不安」「面倒くさい」「本当に改善されるのか」と思っている場合が多いのです。
この状態では一丸となって大きなプロジェクトを始めるのは困難です。
これを解消するためには、最初は小さく始めて徐々に周囲の理解を得ていくしかありません。
例えば、データを印刷して決裁者へ手渡しというアナログなやり方を、メールで決裁者へ送るようにする『デジタイゼーション』。
慣れてきたら、データをクラウドにアップしておき、逐一メールでやりとりをしなくても確認や承認をとることができるようにすれば『デジタライゼーション』の達成です。
このように、デジタライゼーションを通じで業務を変え新しい価値(業務効率の向上)を生み出していくのがDXです。
まずは小さなデジタライゼーションを積み重ねていきましょう。
まとめ
DXを進めるためには、会社全体としてDXへの道筋をつけることが必要です。
すべての業務を一気にデジタル化することは現実的ではありません。
前述したように小さなデジタライゼーションから始めて、ステップを踏んでいきながらDXに取り組んでいきましょう。